世間はお盆休みらしいけれども、自分自身は、どこかに旅行に行こうなんて思うわけでもなく、とりあえず、のんびり読書でもしようと思っていて、とりあえず、手にとって読んでみた本について、アウトプットしておこうかと思う、そんな記事。
『教養としてのラテン語の授業』という本を読む。
タイトルからすると、ひたすらラテン語の文法やら何やらを解説してくれそうな本のイメージもするけれど、実際はそんなことなくて、ラテン語という言語を通してみたときに、日々、自分たちが抱えている辛さだったり、悩みは、大昔のラテン語を使っていた人たちも抱えていたものなんだよ。と語りかけてくれるような、そんな本になっている。
もちろん、様々なラテン語の紹介だったりもあるし、言語体系の流れを解説する部分もあって、それなりに教養が必要とされる部分もあるけれど、どちらかと言うと、ラテン語を使っていた人たちの感性だったり、考え方は、現代にも通じるところがあるよね。なんていったことを読み取れる本になっていると思う。
この本を書いた方は、韓国出身の方で、かなり難しい試験を通ったバチカン裁判所・弁護士だそう。アジアの系譜で、アジア社会を理解している方が、ラテン語を学び、アジアにすむ若者、だったり、社会情勢に押し潰されているような方に向けた本。とも読み取れる。
正直なところ、アジア圏のシステムは、国ごとにそれなりに差異はあるけれど、似たような境遇だったりすることもあり、共感を覚える部分が多い。何より、ラテン語という、現在使われていない言語を通してみる世界観は、かなり新鮮な部分が多い。
「言語は、世界を見るための眼鏡である。」といった類のことを確か、ソシュールという学者が述べていた様に思える。
まさにそのことを実感できる本で、今はもう、失われてしまった言語を操っていた人たちは、どのような世界観で、現実を眺めていたのかを知るきっかけになる。
まぁ、読み進めていくうちに、ラテン語という言語体系がいかに複雑で、習得が困難なのかを理解するわけで、なかなか覚えるのには根気がいるなぁ。って思ったり、何なら、Chat GPTに翻訳してもらうことはできるかなぁ?と思って、Chat GPTに、ラテン語を書かせてみたり。そんなことを面白おかしく楽しんでいたのだけれど、死語になった訳は、ここにあると思う。「使えるようになるまで、めっちゃ時間かかるし、面倒。」
例えば、日本語でさえ、日々絶えず変化しながら、毎年のように新しい単語が生まれ、昔ながらの言葉使いも、ちょっとずつ意味が変化しているわけだけれども、その変化は、いかに楽をして、自分の意思だったり考えを伝えようか。という変化に思える。
どうやら、昔から、人間は楽をしたい生き物のようだ。
ラテン語という面倒な言語は、少しずつ使用者が減り、簡略化して、使用が楽になった言語が、現在残っている。日本語の変化においても、楽をするためのものが多いように思える。
学生が使う言葉は、どちらかと言うと内輪で楽しむためのものだったりするけれど、自分自身の意思伝達のための語彙が少ないことから、様々な場所から借用している、借用語にも思える。「若者言葉=取ってつけたような借用語」という考え。自分自身を表すための語彙がまだ、貧弱なだけ。と捉えることもできる。それを、語彙がある人達(それなりに歳をとった人たち)がこぞって、言葉の乱れが云々ということを言うわけだ。(多分)。
歳を重ねることのメリットは、経験を積み重ねることと、謙虚になることくらいだと思うが、その過程で、様々な語彙を習得しているのでは無いだろうか。だから、別に若者言葉の言葉の乱れ一つに惑わされる必要も無いわけだろうし、また、そんな言語の使い方も過ぎ去るわけで。Hoc quoque transibit(これもまた過ぎ去る)というラテン語に凝縮されているように感じる。
「ラテン語」という死語に触れた後で。
日々、言語は消失している。
コレは、正直なところ、結構常識のように思えてしまうのだけれど、実際には、実感のない部分かもしれない。
言ってしまえば、日本でさえ、「アイヌ語」は、消失の危機にある。
言語の消失が、なぜ、そんなにも注目されていないのだろうか。
それは、きっと、言語が消えることによって、被害を被る実感が無いからだろう。
ただ、実際のところ、言語がなくなることによる喪失は、人類単位でみると、かなり大きい。なぜなら、言語の消失=文化の喪失だからだ。
言語は、その言語を使う人たちが、どの様にこの世界を見ていたのかを表す記号なわけで、その記号を失うことで、その民族が積み上げてきた歴史や、知恵といったものが、全て消えてしまうのだ。
自分は、この書籍を通じて「ラテン語」に触れたわけだけれども、ラテン語という言語体型を知ることで、そもそもの、考え方の違いを理解することができたし、何より、言語に対する感性が一段と深くなったように思える。
「ラテン語」という言語を通して見る世界観は、簡潔に表すなら、「フラットで、今を大切にする」という世界観。言い換えるなら、マインドフルネスといったところだろうか。「今この瞬間」に全神経を集中させていることが伝わってくる。
よく、「人間関係は水のようなものだ」というけれど、ラテン語を使っていた人たちの世界観を通じてみても、このことは昔から同様に感じていたように思える。
ただ一つ、現代になくて、「ラテン語」を使っていた人にある考えは、「死」に対する深い考察かもしれない。Letum non omnia finit.(死がすべてを終わらせる訳ではない)。ラテン語を通じて、こんな声が聞こえてくる。だからこそ、自分自身が、自分をいたわり、ねぎらわないといけないし、自分自身に優しくしてあげないといけないよ。と。この辺りは、セルフコンパッションにも通じる。
「ラテン語」を通じて改めて思う、「今を生きる」大切さ
どの時代の人間も、過去や未来に縛られたりするわけだけれど、それでも、結局は、「今」を大切に生きることが大事だよ。と「ラテン語」も教えてくれる。
Carpe diem, quam minimum credula postero.
(明日にきたいすることなく、今日に意味を持って生きよ)
Carpe diem(カルペ・ディエム)という言葉自体は、「今日を楽しめ」という意味で定着しているラテン語で、映画「今を生きる(dead poet society)」でも度々耳にする言葉だ。
「明日をできる限り信じないで」
このフレーズは、なかなか刺さった言葉だった。
特に、なにも集中していないときとか、何気なく、「明日は…」なんて考え事をするのが癖になっていたようにも思えて、そうなると、たしかに「今」に全力投球できていなかったなぁ。と、そんなことを思う。
本当に嫌なことは、明日の自分に先延ばししたり、特に、自分を苦しめるような思い込みだったり、自分自身に対する叱咤激励(だいたいは自分に対して暴言を吐いていることが多いと思うけれど)、そんな考えを、明日の自分に任せてみたり。この本、『教養としてのラテン語の授業』を読んでいると、それで良いじゃない。と思えてくる。
ほんの少しでも、新しいことに取り組めたなら、挑戦できたなら、それだけでもう、十分スゴイのだ。Summa cum laude(スムマ・クム・ラウデ:最優秀)なのだ。
まずは、何か行動できた自分が、Summa cum laudeであると認めてあげよう。現実は、他者比較をしないと生きていけないような世界線で、いつも誰かと比べられてばっかりだけれども、まずは、自分が自分をSumma cum laude であると自身を持つことも大切なのだ。
きっと、やる気が無いのではない。自分を認めてあげられないのだ。できない自分を直視できていないのだ。ダラけてしまう自分から目を背けたいのだ。
親からも、教師からも、「努力をしなさい」とは言われるけれど、「自分を認めてあげてね」なんて言われたことはあるだろうか?
もし、身近な人に、「自分を認めてあげてね」と言われていたのなら、それだけで、Summa cum laude な環境かもしれない。とはいえ、いつでも、自分で自分をSumma cum laude であると慰めることはできるだろうから、きっと、今からでも遅くはない。
そんなふうに、前向きになれる本だったように思える。
とりあえず、「明日は…」なんていう思考の癖をできるだけ減らそう。そうすれば、きっと、日々、Summa cum laude な日々を送れるだろうし、Carpe diem を体現できるのではないだろうか。
日々、自分自身をすり減らし、慰めなんてものとは程遠い日々を送っているならば、一読してみてはいかがだろうか。この本を読み進めるにつれ、自分の心が落ち着くのが実感できるはずだ。ついでに、ちょっと自慢できる教養が身に付くからオススメ。笑。
[2023 8/7 ~ 8/13:伶丁日記]




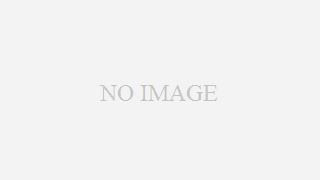

-320x180.jpg)

コメント